Bullying Security
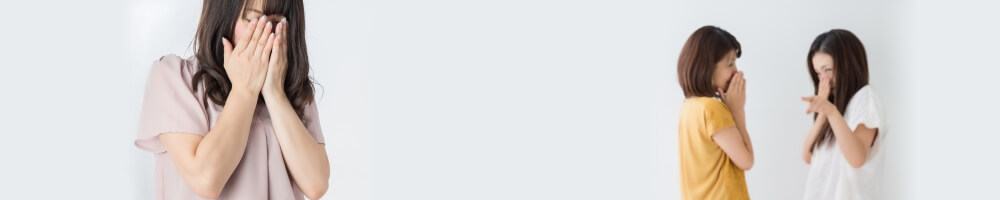

いじめガードサービスとは、子どものいじめから大人のいじめまで、ありとあらゆる「いじめ被害」の内容を具体化するためのサービスです。いじめと言っても被害はさまざまです。近年では子どものいじめばかりでなく、大人のいじめ、ママ友、職場、近所のコミュニティでもいじめが起きるようになりました。こうしたいじめの実態を調査し、証拠を収集して加害者を特定していじめをなくすように働きかけるなど、いじめに遭った方が安心して日常生活を送れるまでサポートします。

現代のいじめは悪質で、インターネットを使うこともあり、誰がいじめをしているのかがわかりにくい特徴があります。そのため、いかにいじめの実態を「見える」化するかが重要なポイントになります。
誰が見ても「これはいじめ」「この状態は放置しておけない」と思えるような証拠を示すことが大事です。
「レンタル警備おじさん」は、見た目が怖いおじさんを派遣する「いじめっ子対策」です。親戚のおじさんのフリをして、いじめの現場に訪れ、いじめっ子を強く叱りつけていじめをやめさせます。いじめっこは自分より弱いとみなした子には「強気」に出ますが、自分より強そうな人にはおとなしくなる傾向があるので、いわゆる「不良」には効果的な対応策になります。

大人のいじめはやり方が巧妙になり、たいていは誹謗中傷による嫌がらせですが、悪口を広め、精神的に追い込もうとします。人の精神はもろく、いじめや嫌がらせが数ヵ月続いただけで精神に深刻な被害を及ぼしたというような事例も見受けられます。

子ども会、婦人会、老人会、など近隣コミュニティのトラブルで「いじめ」が発生するケースがあります。
必要に応じていじめの証拠収集や事前にその地域でのトラブル(騒音・異臭・いじめなど)はなかったか、トラブルが原因で引っ越した人はいないかなどを調査することも可能です。

「ネットいじめ」は、インターネット上のウェブサイトの掲示版などに、特定の子どもの悪口や誹謗・中傷を書き込んだり、いたずらメールを送ったりするため、誰がいじめをしているのかを特定しにくく、いじめそのものが表面化しにくいなどの特徴があります。
そのような場合でも、オンライン調査で証拠を保存し、投稿の削除申請をサポートします。書き込みをした人物を特定する際は、弁護士がサイトの運営会社などに発信者の情報開示請求をしますが、オンライン調査はその前段階での作業になります。
以上が、いじめガードサービスです。
文部科学省は「いじめ」を次のように定義づけています。
『児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行なう心理的又は物理的な 影響を与える行為(インターネットを通じて行なわれるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。』
『「いじめ」のなかには、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報し、警察と連携した対応を取ることが必要である。』(いずれも平成18年度からの定義より)
参照:文部科学省HP『いじめの定義の変遷』より

いじめは、れっきとした犯罪になります。身体に対して危害を加える行為は暴行罪(刑法208条)になり、怪我をすれば傷害罪(刑法204条)が適用されます。
また、断ったら痛めつけるなどと脅して盗みをさせるような行為は、強要罪(刑法223条)に該当し得ます。いじめにありがちな「無視」「仲間外れ」などは犯罪とみなされにくく、いじめをした本人に問い詰めても「嫌いだから無視した」「一度もいじめたことはない」と言われたら、いじめがあった事実を証明しない限り、法律で処罰するのは難しいでしょう。しかし、民法上の不法行為に該当すれば、民事上の責任を追及できる可能性はあります。
これに当てはまらないいじめもありますが、少なくとも、1つ以上当てはまれば「いじめ」と判断していいでしょう。

いじめに遭っている方の望みは、「いじめがなくなる」ことです。いじめられているから話を聞いてほしいわけではありません。励ましてほしいわけでも、なぐさめてほしいわけでもなく「誰からもいじめられなくなる」ことを望んでいると知っていただきたいと思います。いじめには必ず「加害者」がいて、いじめっ子は親御さんに気づかれないところでお子さんをいじめています。家族には見えないことでも、プロにはいじめの実態を「見える」ように記録することもできます。カメラの設置から尾行まで、あらゆる手段を講じて私どもはいじめの実態を暴きます。だから、いじめは必ず解決できると言い切ることもできるのです。
スマートフォンの普及に伴い、昨今ではインターネットを使ったいじめが主流になりました。ネットを使ったいじめの質(たち)が悪い点は、外部から発見されにくいことです。いじめを解決するには、「いじめの実態」と「いじめている現場を押さえた証拠」が必要になるます。いじめは暴行罪・恐喝罪・名誉毀損・侮辱罪・窃盗・信用毀損罪・偽計業務妨害・営業妨害・迷惑行為防止条例の対象になります。証拠を入手するに当たっては、聞き込み調査からオンライン調査までありとあらゆる調査をして、いじめ問題が解決するまでサポートいたします。
いじめで生活に支障が出るようなときは、「いじめガードサービス」をご利用ください。警察に相談することもできますが、事件性がないと判断されると、警察は動いてくれません。警察に相談するとき、被害届を受理してもらえるような証拠・資料を作成できるのもこのサービスの強みです。
Q
いじめの初期対応について
A
基本的には、早期発見・早期対応が必要ですが、経過を見守ることが必要な場合もあります。生徒指導部や管理職と共に充分な配慮をしながら、適切に対応しましょう。
Q
いじめ問題が解決した後の対応について
A
1~3ヵ月程度は、特に注意して見守りましょう。どのように解決したのかにもよりますが、被害者が他の人に変わるだけというようなこともあり、いじめが完全に解消されたかどうかを見極める必要があります。
Q
女性のスタッフに相談することはできますか?
A
弊社にはいじめ対策に取り組んでいる女性スタッフが多数在籍しています。いじめの対処法や解決方法をはじめ、家庭内や人間関係など、さまざまなお悩みの相談にも乗ってくれます。相談は無料で、お話いただいたことが外部に漏れることはないので、お気軽にご相談ください。
Q
会社でいじめに遭ったときはどうすればいいですか?
A
職場でのいじめや嫌がらせは、就業者(労働者)の名誉やプライバシーなどの人格権を侵害する行為に該当し、不法行為として損害賠償責任が生じます。使用者(事業主・経営者)がいじめに加担していた場合はもちろんですが、いじめに関与していなくても職場環境の悪化など、就業者に精神的苦痛を与えたとして、同じように損害賠償責任が生じます。
Q
子どもにICレコーダーを持たせてもいい?
A
要相談だと思います。学校内でのお子さんの様子を知るための「録音」は必要です。鞄の中や教室を移動する際、周囲に気づかれないように袋に入れてもたせてもいいと思います。しかし、他の生徒さんのプライバシーなどには配慮する必要があるので、調査会社と相談するようにしてください。
Q
いじめ調査をする理由は?
A
残念なことに、教育現場や大きな組織では、いじめがあってもその事実や実態を隠そうとすることがあります。学校や職場でいじめに遭っている人をそのような隠蔽体質から守るために、私たちは「いじめガードサービス」を設けました。私たちが調査をするのは、いじめの被害者が安心して学校や職場に通えるように、いじめの有無を証明したうえで責任の所在を明らかにし、二度といじめが起きないようにするためです。
まず、相談することから始めましょう。
現在お持ちのお悩み事、状況、依頼に関する質問や要望などのご相談が可能です。
※docomo・au・softbankなどの携帯電話アドレスはドメイン指定設定により毎月10件以上の「送信エラー」が起こっているため、フリーメール(GmailやYahoo!mail)の利用をおすすめします。しばらく経っても返信が来ない方はお電話にてご確認くださいませ。
Copyright(C) ファミリーセキュリティ. All Rights Reserved.
(C) ファミリーセキュリティ