インターネットが一般化した現代においては、誰でも簡単に情報を発信することができるようになりました。しかし、その反面、誹謗中傷が増加するという問題も生じています。
本記事では、インターネット上での誹謗中傷について、法的な対処法について紹介します。
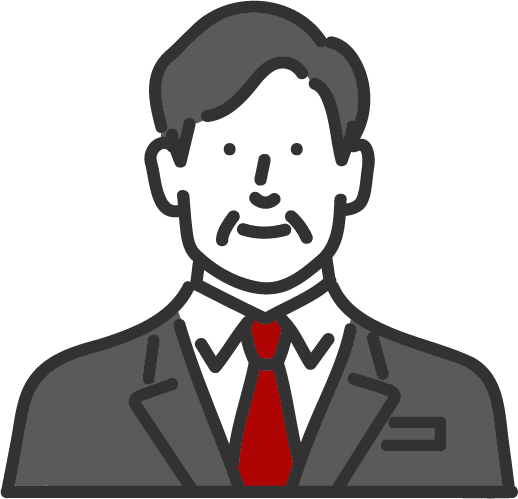
2023年4月14日更新 / 執筆者・監修者 / 山内 和也
1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者ページ
インターネット上の誹謗中傷とは、ネット上で特定の人物に対して悪意のある書き込みをすることを指します。
例えば、SNSやブログ、掲示板などでの匿名性が高い場合、誹謗中傷が行なわれることがあります。
また、特定の人物に対する集団の攻撃が行なわれることもあります。
誹謗中傷が拡散されることで、仕事や人間関係などの日常生活にも大きな影響を与えることがあります。
インターネット上の誹謗中傷には、法的に対処することが可能です。具体的には、名誉毀損罪や侮辱罪などが該当します。
また、インターネット上での書き込みには、電子情報犯罪被害の防止等に関する法律(コンピューター関連犯罪等の規制に関する法律)が適用されることもあります。
被害者は、警察に被害届を提出することで、誹謗中傷の書き込み者を特定することができます。
また、民事訴訟を起こすことで、損害賠償の請求や書き込みの削除を求めることができます。
インターネット上での誹謗中傷は、被害者にとって深刻な問題となります。
法的手続きを踏み、適切な対処を行なうことで、誹謗中傷の拡散を防ぎ、被害を最小限に抑えることができます。
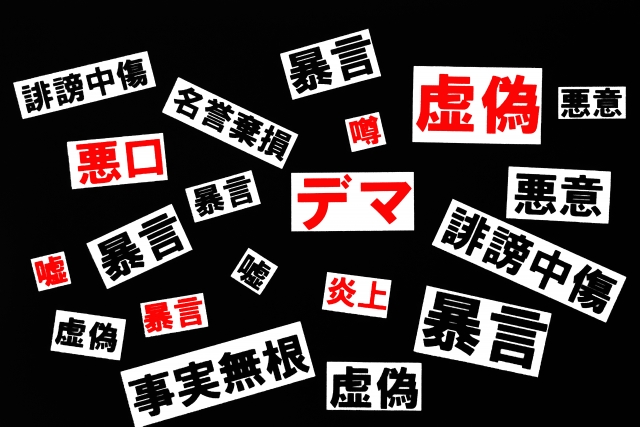
誹謗中傷は、どのような法律に触れるのでしょうか?
自分も知らない間に誹謗中傷していないように気をつけておきたいですし、他人の、自分への誹謗中傷に気が付いて対処することも重要です。
下記の法律を一緒に考えてみましょう。
名誉毀損罪(めいよきそんざい)とは、日本の刑法230条に規定される犯罪で、人の名誉を毀損する行為をその内容とし定義づけています。
刑法上の名誉毀損罪を構成する場合に民法上の名誉毀損として不法行為になることも多いのですが、これはつまり刑法で扱われる判例が民事として扱われ、刑事責任は問われないケースの事を指しています。
公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立されます(刑法230条1項)。法定刑においては3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
ネットや現実社会で誹謗中傷が第一につながりやすい問題が『名誉棄損』です。名誉棄損による被害者への慰謝料請求も行なわれた判例が実際にあります。
慰謝料請求のおおよその目安は原告が一般人の場合10万~50万円、事業主への慰謝料請求は50万円~100万円と言われています。
侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪です(刑法231条)。
侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽いです。
法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されません(刑法64条)。また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらないとされています。
個人のプライバシーに関する情報をネット掲示板やホームページ、電子メールなどで不特定多数の人に流すなどをしても侮辱罪が成立します。
※名誉棄損罪と侮辱罪の違い:
事実の情報を提示した上で著しく社会的評価を低下させた場合が「名誉毀損」、事実の情報を伴わず単に相手の人や事業等を否定し社会的評価を低下させた場合が「侮辱」とされています。

消費者庁に寄せられたインターネットトラブルには、以下のようなものがあります。
注文した商品が届かない、届いた商品が壊れている、サイズが合わないなどの問題があります。また、詐欺の被害に遭った場合もあります。
商品が届かない、届いた商品が説明と違うなどの問題があります。また、オークションサイト上での詐欺の被害に遭った場合もあります。
知らない人からのストーカー行為や、誹謗中傷、プライバシーの侵害などの問題があります。
有料アイテムの購入によるトラブルや、不正なユーザー行為による被害があります。
消費者庁では、これらのインターネットトラブルに対して、消費者の保護と適切な解決に向けた取り組みを行っています。
消費者庁のホームページでは、トラブル解決に役立つ情報や相談窓口の案内などが提供されています。
ネットトラブルに遭遇した場合、相談できる先は以下の通りです。
ネット上での詐欺や誹謗中傷、ストーカー行為など、法律に抵触するトラブルに遭った場合は、警察署に相談することができます。
ネットショッピングやオークション、有料アプリなどの問題に遭遇した場合は、消費者センターに相談することができます。消費者センターでは、消費者トラブルの解決支援や相談窓口を設けています。
ネット上でのトラブルに特化した相談窓口として、ネットトラブル相談センターがあります。ネットトラブル相談センターでは、詐欺や誹謗中傷、プライバシーの侵害など、あらゆるネットトラブルに対応しています。
法律的な問題については、弁護士に相談することもできます。弁護士は、契約書の作成や法律的アドバイス、訴訟手続きの代理などを行ってくれます。
ネット上でのトラブルは、自分で解決するのが難しい場合が多いため、適切な相談先を探すことが大切です。
Q
インターネット上の誹謗中傷の犯人を特定するために、情報開示請求はしてもらえるのか?
A
コンテンツプロバイダから投稿に関するIPアドレスの開示を受けた上で、経由プロバイダに対し投稿者の氏名・住所等を開示請求を行ないます。情報開示請求を行なうには、誹謗中傷の特定が必要になりそのための調査となります。
Q
誹謗中傷をした人の名前をTwitterで晒してもいいの?
A
反撃したいという気持ちがあっても、個人で相手に制裁を加えるような行為をするべきではありません。相手に対して不法行為をしたということで、反対に不利な立場に置かれる可能性があります。
Q
ファミリーセキュリティには専属の弁護士がいるの?
A
顧問弁護士がいます。探偵業務で弁護士が必要となるケースは多いので、一般的に多くのネットトラブルは経験しているかとは思います。ご紹介が必要な方にも対応させて頂いております。
Q
発信者情報開示請求の場合、弁護士費用が別途必要になるんじゃないの?
A
弁護士費用は別途かかります。住所氏名の開示訴訟の平均費用は、30万~40万円とされています。探偵が行なう所在調査は15万~25万円、SNSなどの情報から住所氏名から割り出すことも可能ですが情報次第なので不確定要素が含まれます。
Q
誹謗中傷があった場合、その文章の削除依頼は誰に言えばいいの?直接SNSのヘルプセンターに言うべき?
A
サイトの管理者へ削除の要請をする方法があります各サイトに用意されている、削除申請用フォームから、誹謗中傷を受けた本人でも削除の要請を行なうことができます。
※docomo・au・softbankなどの携帯電話アドレスはドメイン指定設定により毎月10件以上の「送信エラー」が起こっているため、フリーメール(GmailやYahoo!mail)の利用をおすすめします。しばらく経っても返信が来ない方はお電話にてご確認くださいませ。
Copyright(C) ファミリーセキュリティ. All Rights Reserved.
(C) ファミリーセキュリティ